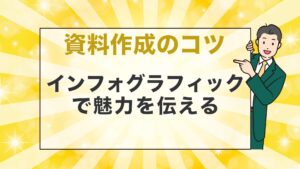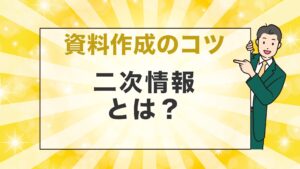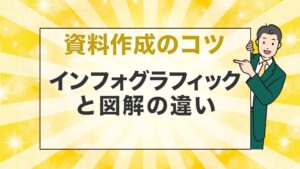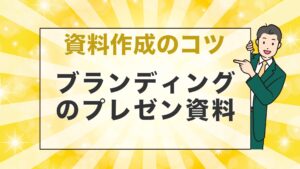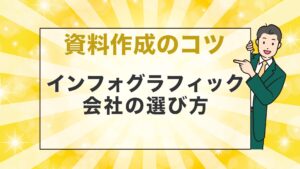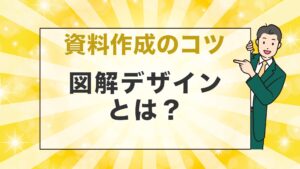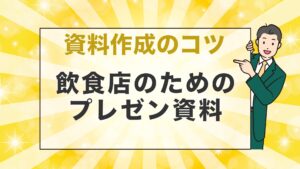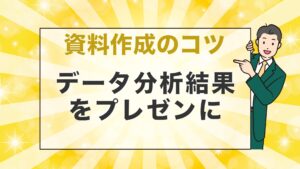プレゼンとは?発表との違いとは?実は明確にわからない方も多いのではないでしょうか。
そもそもプレゼンとは、何をもって成功と言ったら良いのでしょうか。
今回はプレゼンの対象者や発表との違い、ゴールについて解説します。
アウトラインの作りかたや効果を高めるコツなど、プレゼンをうまく進める具体的な準備方法もまとめました。
プレゼンのゴールをおさえて実施できると、クオリティが格段にアップし、ビジネスがスムーズに前に進むようになりますよ。

プレゼンとは何かを把握しよう!
プレゼンとは?対象者と「発表との違い」を確認


実はプレゼンの前提を知らずに実施していた人も多いのではないでしょうか。
次の2点を解説します。
- 誰のためにプレゼンするのか?
- 「発表」と何が違うのか?
プレゼンの対象者とともに発表との違いをおさえておくと、プレゼンのクオリティがアップします。まずは前提から知っておきましょう。
誰のためにプレゼンするのか?
当たり前のようですが、プレゼンは聞き手が対象者となります。
「自分のためではなく、相手のために実施する」スタンスが成功の鍵です。
プレゼン内容を考える時も、以下のように差が生まれます。
- 自分の伝えたいことをプレゼンする → ×
- 相手が伝えられて為になることや嬉しいことをプレゼンする → ⚪︎



プレゼン=相手が聞きたい内容が、成功への近道です。
「発表」と何が違うのか?
プレゼンと発表には明確な違いがあります。
大きな違いは、実施後のゴールです。
プレゼンと発表のゴールを比較すると、以下のように異なります。
| 項目 | プレゼン | 発表 |
|---|---|---|
| 目的 | 提案内容を理解してもらい、次のアクションにつなげる | 自分のアイデアや意見を伝え、相手に理解してもらう |
| ゴール | 相手に動いてもらう、意思決定を促す | 知識を共有する、理解を深めてもらう |
プレゼンは内容の理解だけではなく、相手のアクションにつなげることがゴールになります。
ビジネスでおさえておきたいプレゼンの流れ


プレゼンをどのように行うと成功できるのか?おさえておきたい4つのポイントがあります。
- 相手の現状や悩みを知っておく
- 課題の分析結果を提示する
- 課題に対して解決策を提案する
- 解決策のメリットを伝える
相手の課題解決を目的としたアクションの提案が重要です。それぞれのポイントを詳しく解説します。
相手の現状や悩みを知っておく
プレゼンでの提案のためには、まず相手の現状や悩みを知ることから始めましょう。
ニーズや課題を明らかにしたうえで、解決策を提案する必要があるからです。
現状や悩みを知るには、以下のリサーチ方法があります。
- ホームページやSNS・書籍などの公開情報から情報収集する
- ヒアリングで話を聞く
相手が悩み自体を明確に言語化できていない場合でも、丁寧な情報収集とヒアリングでこちらから課題を洗い出せるとベストです。
課題の分析結果を提示する
次に、相手の抱えている課題を明らかにして提示しましょう。
ビジネスの目標地点と現状との乖離がどの程度あるのか、原因は何なのか、分析結果の提示が相手の気づきにつながるとベストです。
ビジネスでよくある課題には、以下の例があります。
- 中長期的にxx万人にサービスを届けたいが、ターゲットへの認知度が低い
- 長年同一のサービスを運用しているが、今後の方向性が見えない
- 運用の人手が不足しており、サービス拡大に踏み切れない
ヒアリング結果や情報収集した一次情報にもとづいて課題を提示すると、相手は納得感が得られます。
課題に対して解決策を提案する
このステップでは、課題への具体的な解決策を伝えます。
解決策とともに自社が提案できるサービスや製品をあわせて紹介し、具体的な実現の可能性を示しましょう。
たとえば課題と解決策・提案の組み合わせは、以下のとおりです。
| 課題 | 解決策 | 提案 |
|---|---|---|
| 中長期的にxx万人にサービスを届けたいが、ターゲットへの認知度が低い | ターゲットにあわせたSNS発信を強化する | SNS発信や運用を外注できるサービスを紹介する |
| 長年同一のサービスを運用しているが、今後の方向性が見えない | サービス利用者への満足度調査を実施して方向性をつかむ | アンケート調査・結果分析方法と外注サービスを紹介する |
| 運用の人手が不足しており、サービス拡大に踏み切れない | 運用のマニュアル整備とスタッフのリクルーティングを進める | 業務マニュアルの内製ツールを紹介する |
課題の分析結果にそって解決策の背景や理由まで提示できると、提案の説得力が増します。
解決策のメリットを伝える
解決策の先にあるメリットも伝えましょう。
サービスや製品を導入した先のメリットを提示すると、相手は決済や導入の決断が可能になります。
この時、サービスや製品自体のメリットのみを提示しないよう注意が必要です。
以下のようにメリットを提示していきます。
| 課題 | 解決策 | 提案 | メリット |
|---|---|---|---|
| 中長期的にxx万人にサービスを届けたいが、ターゲットへの認知度が低い | ターゲットにあわせたSNS発信を強化する | SNS発信や運用を外注できるサービスを紹介する | 費用対効果の高いSNSを活用し、ターゲットに効率的に情報を届け、認知度アップにつなげる |
| 長年同一のサービスを運用しているが、今後の方向性が見えない | サービス利用者への満足度調査を実施して方向性をつかむ | アンケート調査・結果分析方法と外注サービスを紹介する | 利用者の声をもとに満足度や改善点を把握し、今後のサービス方針を明確にできる |
| 運用の人手が不足しており、サービス拡大に踏み切れない | 業務マニュアルの整備とスタッフのリクルーティングを進める | 業務マニュアルの内製ツールを紹介する | 業務の棚卸しを進めることで、新規スタッフの研修がスムーズになり、他業務にも応用できる |
課題を解決した先に相手のビジネスがどのように前進するのか、相手がイメージできるプレゼンのクロージングを目指しましょう。
知っておきたい!プレゼンの効果を高めるコツ7選


相手に提案を受け入れてもらうには、どのように準備しておくと良いのでしょうか。
次の7つのコツがあります。
- アウトラインにそって作る
- 相手をつかむ導入を考えておく
- 概要をまとめておく
- スライドをわかりやすく作る
- いつもより話しかたに気を配る
- ジェスチャーを効果的に使う
- 準備を十分に行う
相手の立場に立った工夫が、プレゼンの効果を高めます。それぞれのコツを解説します。
アウトラインにそって作る
プレゼンはアウトラインにそって流れと構成をつくりましょう。
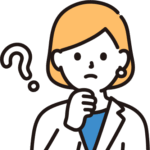
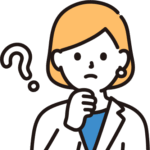
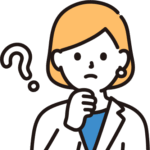
相手にわかりやすく論理的に提案を伝えるには、型があります。
自己流の構成作成で時間を浪費しないためにも、アウトラインの作りかたは重要です。
以下が基本的なアウトラインです。
- 導入:相手の現状や悩み
- 課題提起:課題と分析結果の提示
- 解決策:課題にもとづいた具体的な解決策、自社サービスや製品の紹介
- 結論:解決策を実行するメリット、次のアクションをうながすクロージング
アウトラインをおさえたプレゼンは、プレゼンする側も説明しやすいのがメリットです。
なお、各パートの論理構成にも型があります。詳しくは以下の記事を参考にしてください。
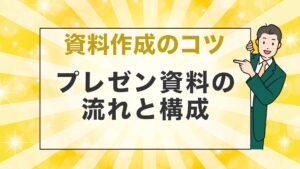
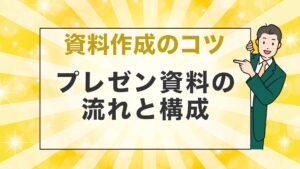
相手をつかむ導入を考えておく
プレゼン冒頭の導入では、相手の関心を引きつけられる工夫を考えてみましょう。
説明を聞く側は「自分が興味を持てる内容か」「自分のビジネスにベネフィットがある内容か」を早めに知りたいと思っています。
例えば詳細説明に入る前に、以下のような導入が可能です。
- 結論の一部を先に伝えて相手を引きつける
- 相手がプレゼンの必要性を実感できるように背景を丁寧に伝える
- 目次でプレゼンの全体像を伝えて相手の関心を高める
プレゼンへの関心が高まった状態なら相手の反応もよくなり、説明する側も進めやすくなります。


概要をまとめておく
プレゼン全体の概要をまとめておくと、ピッチプレゼンに役立ちます。
ピッチプレゼンとは、短時間でのプレゼンのことです。
プレゼン相手によっては、「後ろの予定がせまっている」「同じような提案が複数続いているので手短に聞きたい」など、時間に制限が設けられている場合があります。
このような時、要点と結論のみ説明できればプレゼンのチャンスを逃さずにすみます。
追って詳細を伝えるには、以下の工夫が可能です。
- 資料やWebページに誘導する
- サービス概要をまとめた動画を共有する
プレゼンは相手の時間にあわせて行うものです。いざという時のために準備しておきましょう。
スライドをわかりやすく作る
プレゼン内容の魅力を存分に伝えるためにも、スライドはわかりやすく作りましょう。
「わかりやすい」と感じると、相手はプレゼンの内容により集中できます。
以下のように、全体のバランスや視線を意識するのがポイントです。
- 直感的に理解できるデザインになっている
- スムーズに視線が流れるレイアウトになっている
- 重要な情報が自然に目に入る配置・色使いになっている
スライド作成の作業中は、ついデザインに凝ってしまうことがあります。しかし、相手に理解してもらいやすいかを忘れずに作業を進めましょう。
具体的なデザインのポイントは関連記事も参考になります。
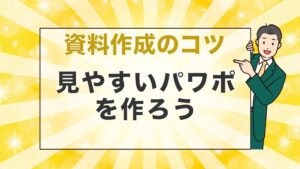
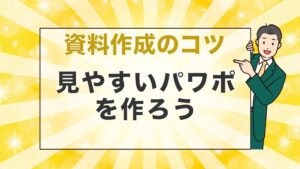
いつもより話しかたに気を配る
プレゼンの成功には、話しかたも重要です。
プレゼン内容を相手が理解するには、スライド内容とあわせて、話されている情報がわかりやすいかも大切になってきます。
自分なりに「聞きやすさ」を実現するために、以下を心がけてみましょう。
- 相手に十分聞こえる声の大きさで話す(会場が広い場合はマイクに声が入るように話す)
- 特に伝えたいポイントでゆっくり話す、繰り返すなど強調の工夫をする
- 「あー」「えー」など余計な発声(フィラー)が混じらないように注意する
普段の会話と話しかたが異なりますので、あらかじめ練習をおすすめします。
ジェスチャーを効果的に使う



プレゼンには、ジェスチャーも取り入れてみましょう。
表情や手の動きからエモーショナルに伝えると、相手の共感につながります。
また、プレゼンにリズムが生まれて提案の熱量を伝えるのにも効果的です。
慣れていない方でも、以下のシンプルなジェスチャーなら挑戦しやすいのではないでしょうか。
- 強調したいポイントでは手でスライドを指し示す
- 提示するポイントの数を指で示す
ジェスチャーをするためには手を空けておく必要もあります。
スライド送りをPCで操作せずにクリッカーを使うと、画面に集中せず相手の顔も見られるのでおすすめです。
準備を十分に行う
プレゼン前には、自分なりに十分な準備をしておきましょう。
プレゼンを聞く側の視点で内容を見直してみると、色々な改善点が見つかるものです。
また、プレゼンに慣れていない方は準備自体が自分の安心感につながります。
以下が具体的な準備内容です。
- 資料を読み返してチェックする
- 台本を本番同様に読んでみる
- 持ち時間内に収まるか計っておく
- スライドの投影が支障ないか確認しておく
- リハーサルを録画して見返す、あるいは他の人にチェックしてもらう
気づいた修正ポイントは本番までに見直しておきましょう。
まとめ:プレゼンはビジネスを前に進める基本スキル


今回はプレゼンの対象者やゴールのほか、アウトラインの作りかたや効果を高めるコツなど、プレゼンをうまく進める具体的な準備方法もあわせて解説しました。
プレゼンは発表と異なり、相手に次のアクションをうながすことが目的です。
この記事で学んだ方法を使って、ぜひ相手が内容に納得して、提案を受け入れてくれるプレゼンを目指してください。