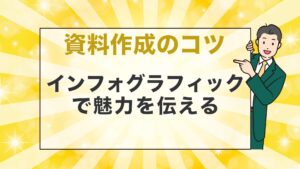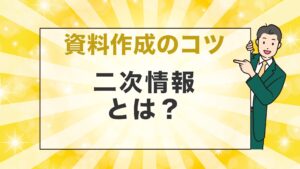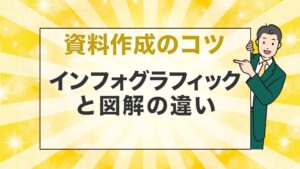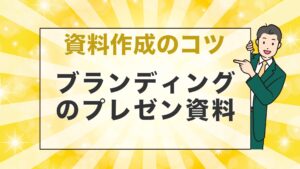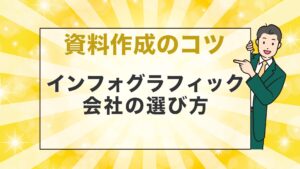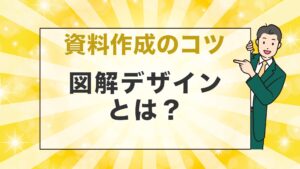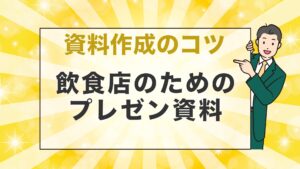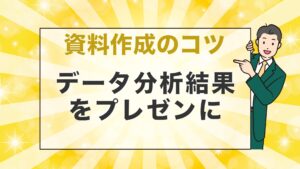「プレゼン資料でグラフをわかりやすく見せたいのに、作り方が分からない」
プレゼン資料にグラフを盛り込む時には、どんなことをおさえておくと良いのでしょうか。
今回はプレゼン資料での、わかりやすく効果的なグラフのつくりかたを解説します。
グラフの種類別におさえておきたいコツやデザインのヒント、参考事例もまとめました。
この記事の内容をいかせば、グラフのデータを根拠にして説得力のあるプレゼンができるようになります。

プレゼンに使うグラフは、コツをおさえておくと格段に見やすくなりますよ。
プレゼン資料のグラフはひと目で伝わることが大切


プレゼン資料のグラフは、「読ませるもの」ではなく「見せるもの」と考えましょう。
何を示しているのか、何を伝えたいのか、ひと目で伝わるとプレゼンがスムーズに進みます。
そのためには以下の点で情報を整理する必要があります。
- 伝えたい点が目立っている
- 伝えたい点以外は目立たないように表現したりカットしたりする
相手に考えさせずに、数値のインパクトが見やすく伝わるグラフがベストです。
プレゼン資料の見やすいグラフ3原則


グラフの種類によらず、見やすいグラフには共通点があります。
以下3つのポイントをまとめました。
- 伝えたいことにそって集計されている
- 色数が絞られている
- データラベルが整っている
グラフを作成したとき、プレゼン資料に掲載したときにチェックしたいポイントです。
伝えたいことにそって集計されている
グラフは伝えたい内容にそって集計しましょう。
データをそのまま見せるだけでは、相手にはインパクトが伝わりません。
伝えたい内容は何か?例えば以下のようにテーマにそって集計方法を考えるとわかりやすいです。
| 伝えたい内容 | ポイント |
|---|---|
| 年代別の推移 | 増えているのか、減っているのかを時系列で示す。 |
| 属性別の数値 | 数値や比率の差を比較し、特徴を明確にする。 |
| データの関連性 | 傾向が似ているのか、関連があるのかを示す。 |
色で伝えたい内容が可視化されている
見やすいグラフは、色を効果的に使って伝えたい内容を可視化しています。
エクセルのデフォルトで作成されるグラフは色の数が多い傾向があります。
一見カラフルで明るい印象ですが、どの情報を見たらよいのかわかりづらいのがデメリットです。
そこで以下のようにひと手間加えると見やすくなります。
- グラフの色を同系色に統一する
- 特に大切なデータを濃い色に変える
- 伝えたい内容に直接関連しないデータは薄い色やグレーに変える
コーポレートカラーやブランドテーマの色を取り入れると資料に統一感もうまれて効果的です。
データラベルが整っている
データの数値ラベルが整っているだけでも、グラフは見やすくなります。
ラベルとグラフが重なっていたりラベルの文字同士が重なっていたりすると数値が読み取れにくいため、読み手にストレスをあたえてしまいます。
グラフはデフォルトのままにせず、見にくいラベルがないか確認して以下のように整えておきましょう。
- 文字サイズを変える
- 文字に重ならないようラベルを移動させる
- 目盛りの補助線や縦軸を削除する
一見当たり前のひと手間ですが、読み手のストレスがなくなるだけでも印象が変わります。
【グラフ別】 データを見やすくまとめる時のポイント


グラフは伝えたい内容によって種類が異なります。
利用頻度の高い4種類のグラフについて、見やすくするポイントをまとめました。
- 散布図
- 棒グラフ
- 折れ線グラフ
- 円グラフ
データのインパクトや変化など、「見てわかる」ようにするためのポイントを解説します。
散布図
散布図は横軸と縦軸にそれぞれ別の量をとり、データをプロットして相関関係を表すグラフです。
強調したいデータ範囲にフォーカスして表示すると、見やすいグラフになります。
例えば以下の調整方法があります。
| 調整方法 | ポイント |
|---|---|
| 年齢と年収の相関図 | 年齢の軸は生産年齢に絞り、未成年や定年後の世代を省く。 |
| 身長と体重の相関図 | 平均から大きく外れる数値は除外し、見やすくする。 |
集計範囲の調整のみで、データの関係性をより視覚的に表現できます。
棒グラフ
棒グラフは、データの大小を視覚的に表すグラフです。
縦軸または横軸いずれかにデータ量、別軸に比較項目を取り、棒の長さで項目ごとの差を示せます。
単純に作成すると棒の太さや余白が見にくい場合があります。また、数値が伝わりづらい場合もあります。
データ量を正しく比較するために、以下の調整が必要です。
- 棒の幅は適性か?
- 太すぎるなら細くして余白をあける
- 細すぎるなら太くして余白が空きすぎないようにする
- 目盛り線は見やすいか?
- 細かく入りすぎているようなら表示幅を調整する
- 余計な補助線は削除する
- ラベルは見やすいか?
- 伝えたい数値の文字を目立たせる
- ラベル同士が重なっている場合は位置を変えたり伝えなくて良いラベルを削除する
見やすい棒グラフからは、増減や比率がわかりやすく伝わります。
折れ線グラフ
折れ線グラフは、時系列などで連続するデータの変化を追うためのグラフです。
横軸に年や月などの時間、縦軸にデータ量をとって、データを線で結んで作成します。
以下のポイントに気をつけてください。
- 余計な補助線で見にくくなっていないか?
- 余計な補助線は削除する
- 目盛り線の幅が細かすぎないか?
- 表示の最低数値を変更する
横軸と縦軸それぞれの表示幅が適性なら、データ変化がひと目で見やすいグラフになります。
円グラフ
円全体の割合を100%として、項目の構成比を表したグラフです。
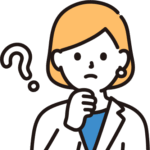
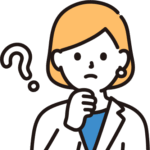
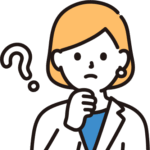
円グラフは扇形の面積で比率の大小を表します。
特に集計項目が多い場合、デフォルトの円グラフは見づらくなりがちなため要注意です。
以下がチェックポイントです。
- 凡例が見やすいか?
- データはグラフ内に表示した方が見やすくなる
- 項目数が多すぎないか?
- ドーナツ型にして中心を空白にするとスッキリ見せられる
- 色が多すぎないか?
- 同系色の濃淡で塗り分ける(上位:濃い → 下位:薄い)
形がシンプルな分、比率の大小をひと目で伝えるのがコツです。
グラフをさらに見やすくさせる5つのポイント


グラフはディティールにも気を配ることで、さらに見やすくなります。
以下5つのコツをまとめました。
- 単位の記載方法
- 凡例(はんれい)の記載方法
- データ母数の示しかた
- 色の強弱
- 数字や文字の強弱
デフォルトのグラフを作成したままにせず、ひと手間加えるだけで見やすさがアップします。
単位の記載方法
グラフの基本ではありますが、単位は必ず表示しておきましょう。
数値のみではグラフが何を表現しているのかが分かりづらいものです。グラフの軸に必ず表示します。
単位のみを表示しておけば伝わるため、データを確認して以下のように表示しておきましょう。
| データの種類 | 推奨される単位表示 |
|---|---|
| 割合 | % |
| 人数 | 人/千人 |
| 金額 | 円/万円 |
デフォルトでは表示サイズが大きすぎる場合があるので、適宜調整すると見やすくなります。
凡例(はんれい)の記載方法
グラフで表示しているデータの説明です。
グラフの棒や線が何を示しているのかを色別などで表示します。
グラフを作成すると凡例も自動的に作成されます。デフォルトではグラフ外に表示されていますが、グラフ内に表示したほうが直感的に伝わる場合もあります。
デフォルトの凡例が見にくい場合は調整しましょう。
データ母数の示しかた
データ母数は標本数・サンプル数のことです。
母数が大きく偏りがないほどデータの誤差が小さくなり、グラフの信頼性が上がります。
例えば「n=XX(人)」と表示があれば「xx人のデータをグラフ化している」と分かります。
表示は目立たないサイズで構いませんが、グラフとあわせて必ず表示しておきましょう。
色の強弱
プレゼン資料全体にも言えますが、色の使い方はグラフでも重要です。
グラフでは色がついたデータがより強調されます。また、色が多すぎると伝えたいことが分かりづらくなります。
以下の手順を加えると色数をおさえた見やすいグラフになります。
- 伝えたい内容が何か確認する
- 伝えたい部分のみに色をつける
- 伝えたい部分以外はグレーや同系色の薄い色に変える
色に強弱をつけて、データの強弱も表すのがコツです。
数字や文字の強弱
グラフでは、データの大小が数字や文字でも表現されます。
比率の大きさやデータの伸びなど、数字で表されるインパクトは相手にぜひ伝えたいところです。
以下の手順で数字や文字に強弱をつけておくと、グラフ内で効果的にデータを見せられます。
- 伝えたいデータ項目が何か確認する
- 伝えたい数字や文字は大きくする/太字にして目立たせる
- 伝えたい数字や文字以外はグレーに変える/削除する
必要のない数字や文字を目立たせない工夫も、伝えたい内容を強調するテクニックです。
グラフが見やすいプレゼン資料事例


プレゼン資料では、グラフはどのように盛り込まれているのでしょうか。
実際のプレゼン資料でグラフに盛り込まれている参考事例をグラフの種類別にまとめました。
見やすいポイントもあわせて解説します。
比較グラフ
会社案内の資料内で、男女比率の表現に棒グラフが使われている事例です。
同系色の青色のみで男性/女性を表現して、同じページ内の数値やグラフと色の統一感を保っています。
総従業員/管理職での男女比率の違いがひと目でわかるグラフです。違いを見せたい項目にあわせて集計されているとわかります。
出典:株式会社リブセンス会社紹介資料 /Invent the next common.
棒グラフ
サービス紹介の資料内で従業委員数の推移を棒グラフで表現した事例です。
グラフ全体は同系色でまとまり、色のばらつきによるストレスがありません。
従業員数と売上額の上昇を矢印のビジュアルでも強調しています。
さらにグラフ内に受賞歴やサービスローンチ情報なども記され、企業の歩みまでひと目でわかるグラフになっています。
出典:BizMowのサービス内容
積み上げグラフ
積み上げグラフにより正社員数内の女性比率を表現したグラフです。
あえて女性比率のみを強調して、社員に占める割合が過去最大となっている点がひと目でわかります。
伝えたい数値は引き出し線や文字サイズを変えて、グラフ内で埋もれないような工夫もされています。
別軸のユニバーサル雇用比率は折れ線グラフで表現し、かつ補助線の表示がないため、伝えたいデータが見やすいグラフです。
出典:freee Movement Deck
折れ線グラフ
折れ線グラフで正社員数の推移を表現したグラフです。
横軸の時間、縦軸の人数とも会社設立当初から現状までの範囲が適正に設定されています。
グラフ全体で正社員数の増加傾向での推移が表現されており、企業の成長が見やすく伝わります。
出典:スマートキャンプ株式会社 会社紹介資料 / companydeck


円グラフ
求職者向けに職種の比率を円グラフで伝えるグラフです。
コーポレートカラーの緑色を用いて、色の濃淡で比率の差を伝えています。上位3種は数値もグラフ内に表示して、具体的な割合もひと目でわかります。
出典:エンジニア職/新卒向け会社紹介資料(テックファーム株式会社)


まとめ:見やすいグラフでプレゼンの説得力アップ!


今回は、プレゼン資料での見やすいグラフの必要性、グラフの種類別におさえておきたいコツやデザインのヒント、参考事例を解説しました。



グラフはデータによって根拠を示し、プレゼンの説得力を左右します。
この記事で学んだ方法を使って、ぜひ見やすく効果的なグラフをプレゼン資料に盛り込んでください。