業務量が多すぎてお困りではありませんか?その業務、自動化しましょう!
お仕事自動化ラボでは、お客様のビジネス課題に基づいて完全オーダーメイドで業務自動化フローを構築するサービスを提供しています。
ルーチン業務を自動化して、あなたはよりクリエイティブな仕事にチャレンジ!
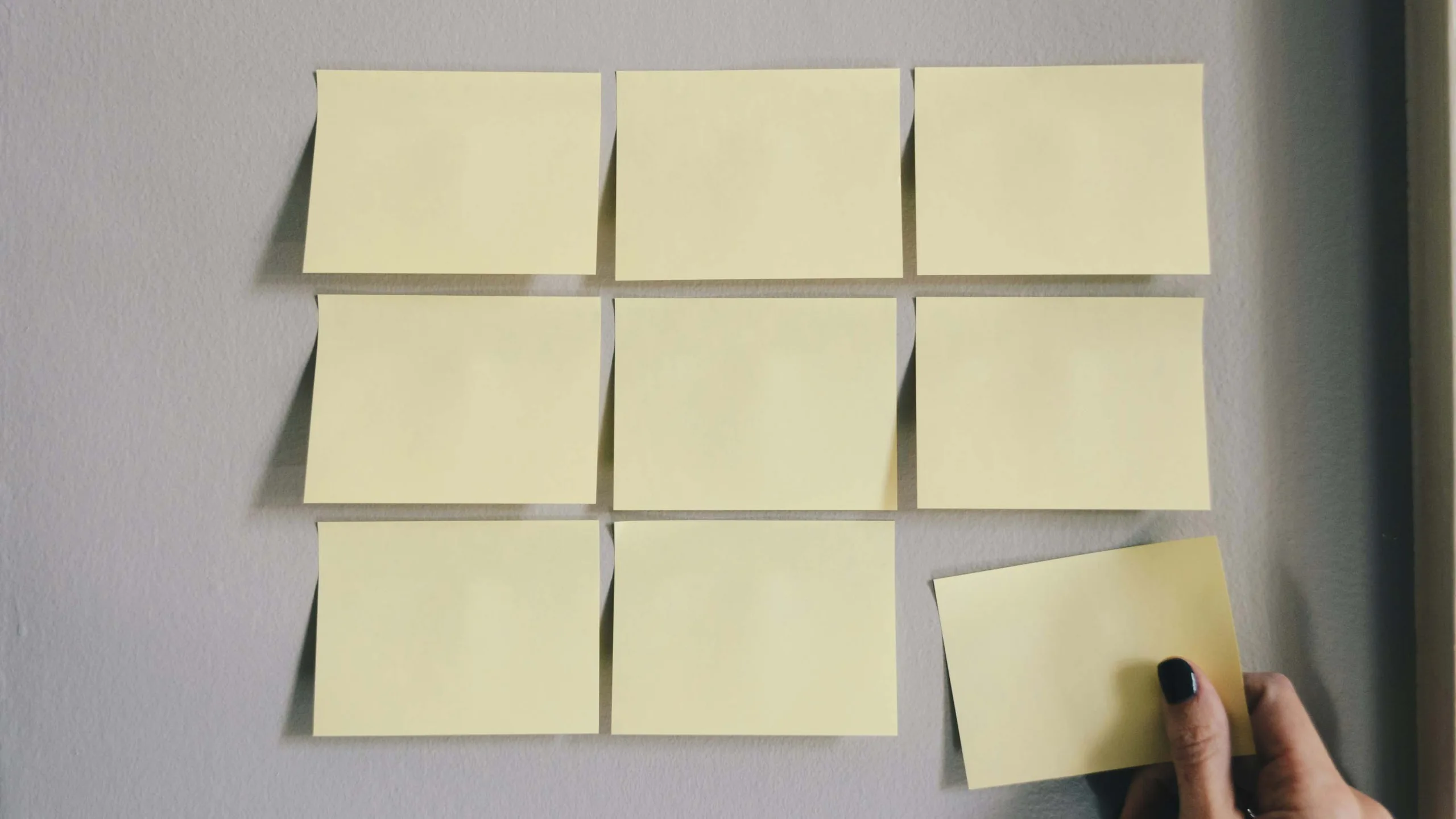
業務量が多すぎてお困りではありませんか?その業務、自動化しましょう!
お仕事自動化ラボでは、お客様のビジネス課題に基づいて完全オーダーメイドで業務自動化フローを構築するサービスを提供しています。
ルーチン業務を自動化して、あなたはよりクリエイティブな仕事にチャレンジ!
「アイデア出しといっても、何から始めればいいのか分からない…」
「チームで話し合っても、いつも同じようなアイデアばかり」
「新しい視点が欲しいのに、なかなか浮かばない」
こんな悩みを感じたことはありませんか?
企画や商品開発、マーケティングなど、ビジネスのさまざまな場面で「アイデア」は欠かせないものですが、常に新しい発想を求められるのは、簡単なことではありません。
しかし、実はアイデア出しは“才能”ではなく、“方法”でカバーすることができます。
特に有効なのが、「フレームワーク」を活用するという手法です。フレームワークとは、考えを整理したり、発想を広げたりするための“型”のようなもの。
 ビジネスウーマン
ビジネスウーマンこれを使えば、だれでもアイデアを効率的に引き出せるようになります。
この記事では、ビジネスシーンで使える「アイデア出しのフレームワーク」を10個厳選してご紹介します。
実際の活用方法やおすすめの使い分けも解説しているので、「考えるのが苦手」「アイデアが出ない」と感じている方でも、明日からすぐ実践できる内容です。


この章では、アイデア出しにフレームワークを用いるべき理由について解説しています。フレームワークを使うべき理由を学びましょう。
「発想力がある人はすごい」「自分にはセンスがないから無理」
そんなふうに感じている方は多いかもしれません。しかし、実際にクリエイティブな仕事に携わる人たちは、必ずしも“ひらめき型”ばかりではありません。



彼らがよく使っているのが、「フレームワーク」という考え方の補助ツールです。
フレームワークとは、思考を整理したり、視点を増やしたりするための「枠組み」のこと。これを活用することで、頭の中でぼんやりしていたアイデアの種を“見える化”し、形にしやすくなります。
たとえば、何もない状態で「新しい商品を考えてください」と言われても、いきなりアイデアは浮かびませんよね。
しかし、「既存の商品を“減らす・置き換える・逆転する”としたら?」という視点(これはSCAMPER法というフレームワークの一部です)を与えられれば、自然と発想が動き始めます。
このように、フレームワークは思考のきっかけや“方向性”を与えてくれます。
発想に行き詰まってしまうときも、特定の視点を示してもらうことでアイデアの幅が一気に広がることがあるのです。
フレームワークの最大のメリットは、「誰でも使える」という点です。思考の癖や過去の経験に縛られず、意図的に視点を切り替えることができるため、属人的なアイデア出しから脱却できます。
チームでのブレインストーミングやワークショップでも共通の“言語”として機能し、議論の質やスピードを高めてくれるのもポイントです。
共有しやすく、再現性が高いため、組織全体でアイデアの質を底上げできるのです。
アイデア出しに迷ったときこそ、こうしたフレームワークの力を借りてみましょう。それは、あなたの思考に“地図”を与えるようなもの。闇雲に探すのではなく、目的地に近づくための道筋を明確にしてくれるはずです。


アイデアを出すとき、「何もない状態」から考えようとするのは意外と難しいものです。
ここでは、個人でもチームでもすぐ使える、実践的なフレームワークを10種類ご紹介します。
それぞれの特徴と使い方、そしてビジネスシーンでの活用例を交えながら解説しますので、自分に合った方法をぜひ見つけてみてください。
思考を視覚的に広げる、発想の出発点におすすめの手法です。
マインドマップは、中心となるテーマから放射状に関連語や連想ワードを広げていくことで、思考を整理し、発想を促進するフレームワークです。
トニー・ブザンによって提唱されたこの手法は、創造的なアイデアを引き出すための定番として世界中で活用されています。
使い方はシンプルで、紙やホワイトボード、専用アプリを使って「中心テーマ」をまず真ん中に書きます。そこから自由にキーワードを枝分かれさせ、さらに細かく思いついた言葉をつなげていきます。



視覚的に全体を把握しやすく、思考が一方向に偏らないのが特徴です。
複数人で共同作業する場合も、アイデアの出し合いがスムーズになります。
活用シーン
・企画立案時のアイデア整理
・記事や動画などの構成案づくり
・研修やワークショップでの思考トレーニング
既存のものに「変化」を加えて、新たなアイデアを引き出す発想法です。
SCAMPER法は、アイデアが浮かばないときに役立つ「発想のヒント集」として機能するフレームワークです。以下の7つの視点から既存のものを変化させ、新たな可能性を探ります。
たとえば、「使い捨ての紙コップ」を「環境配慮型の素材に代用(S)」したり、「カップとストローを一体化(C)」したりといった具合です。ひとつのアイデアに対し、順にこれらの視点で問いかけていくことで、複数のアイデアを発想できます。
活用シーン
・商品開発・サービス改善
・既存企画のブラッシュアップ
・発想が煮詰まったときの打開策
自由な意見を出し合い、思わぬアイデアの化学反応を狙う定番手法です。
ブレインストーミング(略して「ブレスト」)は、複数人がアイデアを出し合うことで発想を広げていく手法です。1940年代にアレックス・F・オズボーンが提唱し、今では世界中の企業で会議手法として活用されています。
ポイントは、次の4原則です。
この原則に沿って、まずはできるだけ多くの意見を出し合い、その後で整理・評価を行います。意外な組み合わせや派生アイデアが生まれることも多く、チームならではの創発的な力を引き出せます。
活用シーン
・新商品やキャンペーンの企画会議
・チームでの問題解決ワークショップ
・社内研修やクリエイティブ研修
複数の情報を「グルーピング」して、新たな構造や関係性を見つけ出す手法です。
KJ法は、文化人類学者・川喜田二郎氏が考案した日本発のアイデア整理法です。大量の情報を付箋やカードに書き出し、それらをグループ化して関係性やテーマを導き出すのが特徴です。
ステップは以下の通り:
直感的にグループ分けを行うため、論理に縛られず新しい気づきが生まれやすいのが魅力。特に複雑な課題やアイデアの断片が多い場合に効果を発揮します。
活用シーン
・マーケティングリサーチ後の情報整理
・アイデアの分類や戦略立案
・ワークショップや合意形成の場面
「視点のチェックリスト」で、既存の発想に変化を加える方法です。
ブレインストーミングの創始者、アレックス・F・オズボーンが提案したチェックリスト型のフレームワークです。アイデアに対して次のような質問を投げかけることで、新しい方向性を見つけます。
まるで「発想の道しるべ」のように、質問形式で思考を誘導するのがこの手法の特長です。
質問に対してYes/Noを出すだけでなく、その理由を深掘りすることで、多角的なアイデア展開が可能になります。
活用シーン
・発想の広がりが止まったときの打開策
・新規企画のアイデア肉付け
・定例的なプロジェクトの見直し
目標やテーマを“分解”して、アイデアの幅を広げるためのフレームワークです。
マンダラートは、3×3のマスを使って発想を広げる日本発のフレームワークです。野球の大谷翔平選手が高校時代に目標設定に用いていたことでも話題になりました。
まず中心のマスに「テーマ」や「課題」を記入し、周囲の8マスに連想される要素やキーワードを書いていきます。さらにその8つをそれぞれ中心にして、新たに8つの関連キーワードを展開していきます(最大81マス)。



これにより、具体的な視点やアクションが自然と見えてきます。
シンプルながら深掘り力があり、目標設定やコンテンツの企画など、幅広い活用が可能です。
活用シーン
・新規事業の要素洗い出し
・目標達成のための行動整理
・SNSやブログのネタ発掘
事業全体を“見える化”し、アイデアの検証やブラッシュアップに使える手法です。
ビジネスモデルキャンバスは、1枚のシートに9つの要素を書き出すことで、事業の全体像を俯瞰できるフレームワークです。アレックス・オスターワルダーによって提唱され、スタートアップから大企業まで広く使われています。
9つの要素は以下の通りです。
これらを視覚的に配置することで、抜けや矛盾を発見したり、新しい発想のヒントを得たりできます。
事業アイデアを一枚の紙に落とし込めるため、チームでの共有やピッチ資料の整理にも最適です。
活用シーン
・新規ビジネスの企画立案
・既存ビジネスの見直し
・投資家や社内向けプレゼンの土台づくり
問題や目標を“分解”して、課題解決や具体的行動につなげる思考整理法です。
ロジックツリーは、テーマを階層的に分解し、思考の抜けや偏りを防ぐためのフレームワークです。Whyツリー(なぜ?を繰り返す)とHowツリー(どうやって?を繰り返す)の2種類があり、目的に応じて使い分けます。
たとえば「売上が伸びない」という問題に対して「なぜ?」を繰り返すことで原因を深掘りし、「どうやって?」を使えば具体的な打ち手を導き出せます。



ロジカルシンキングに基づいているため、思いつきや感覚に頼らないアイデア出しが可能になります。
活用シーン
・課題分析や改善策の洗い出し
・提案資料の構成整理
・メンバーとの意見共有・すり合わせ


基本の“問い”を使って、アイデアを具体化・体系化する古典的かつ有効な手法です。
5W1Hは、以下の6つの問いを軸にします。
これらの軸を元に、情報を整理・深掘りするフレームワークです。ビジネスだけでなく、ライティングやプレゼン、マーケティングにも広く応用されています。
たとえば「新しいイベントを企画する」場合、それぞれの問いに対して答えることで、アイデアが自然と肉付けされていきます。また、抜けや曖昧な点にも気づきやすくなります。
直感的に使えるうえに、フレームに沿って考えるだけでアイデアを“企画”として形にしやすくなるのが特徴です。
活用シーン
・新企画や提案書の骨子づくり
・プロジェクトの設計と説明
・サービスやプロダクトの見直し


「逆から考える」ことで、見落としていた発想に気づける応用型フレームワークです。
リバースブレインストーミングは、通常のブレストとは逆に「どうすれば失敗するか?」「どうしたら最悪の結果になるか?」といった逆方向の問いからアイデアを出す発想法です。
一見ネガティブな発想ですが、「失敗要因を先にあぶり出す→それを防ぐにはどうする?」という流れにすることで、問題点の可視化や実用的なアイデアの発見につながります。



逆方向から思考することで、普段とは違う視点が得られるのが大きな利点です。
活用シーン
・リスクの洗い出し
・改善策や安全策の検討
・斬新な切り口を求められるとき




アイデア出しのフレームワークは、ただ「使えばよい」というものではありません。より効果的に活用するためには、いくつかのポイントと注意点を押さえておく必要があります。



まず大切なのは、「何のためにそのフレームワークを使うのか」をはっきりさせることです。
たとえば、発想を拡げたいのか、課題を深掘りしたいのか、具体的な施策に落とし込みたいのか。その目的によって選ぶべき手法は異なります。
無理にすべての手法を使う必要はありません。目的と課題に合わせて適切に使い分けることで、思考の無駄を省き、効率的にアイデアを引き出すことができます。
フレームワークの多くは、個人でもチームでも活用できますが、進め方は少し異なります。
たとえばブレインストーミングやKJ法は、複数人での意見共有に向いていますが、マインドマップやロジックツリーは個人でも深い思考を促すのに効果的です。
また、チームで使う場合は「全員が手法の意味を理解しているか」「意見を出しやすい場が整っているか」も重要な要素になります。
フレームワークを使って多くのアイデアが出ても、それだけで終わっては意味がありません。出てきたアイデアを「選び」「まとめ」「実行する」ためのプロセスも同時に設計しておきましょう。
たとえば、SCAMPERで出たアイデアを5W1Hで具体化する、KJ法でまとめたグループをビジネスモデルキャンバスで検証する、といった“組み合わせ”も効果的です。思考をつなげていく工夫が、現実的なアウトプットへと導いてくれます。


アイデア出しにおいて、「ひらめき」や「感覚」に頼ることは、再現性やチームでの共有という点で限界があります。
しかし、今回ご紹介したようなフレームワークを活用することで、思考の幅を広げたり、発想のきっかけを得たりといったことが、誰にでも実現できるようになります。



ポイントは、「目的に応じた使い分け」と「継続的な実践」です。
最初は難しく感じても、何度か使っていくうちに自然と頭の中でフレームができてきます。そうなれば、日常の会話やメモでも自然とアイデア体質に近づいていけるでしょう。
チームでも個人でも応用できるアイデア出しフレームワーク。ぜひ、明日からの企画や会議に取り入れて、新しい視点と可能性を見つけてみてください。
業務量が多すぎてお困りではありませんか?その業務、自動化しましょう!
お仕事自動化ラボでは、お客様のビジネス課題に基づいて完全オーダーメイドで業務自動化フローを構築するサービスを提供しています。
ルーチン業務を自動化して、あなたはよりクリエイティブな仕事にチャレンジ!