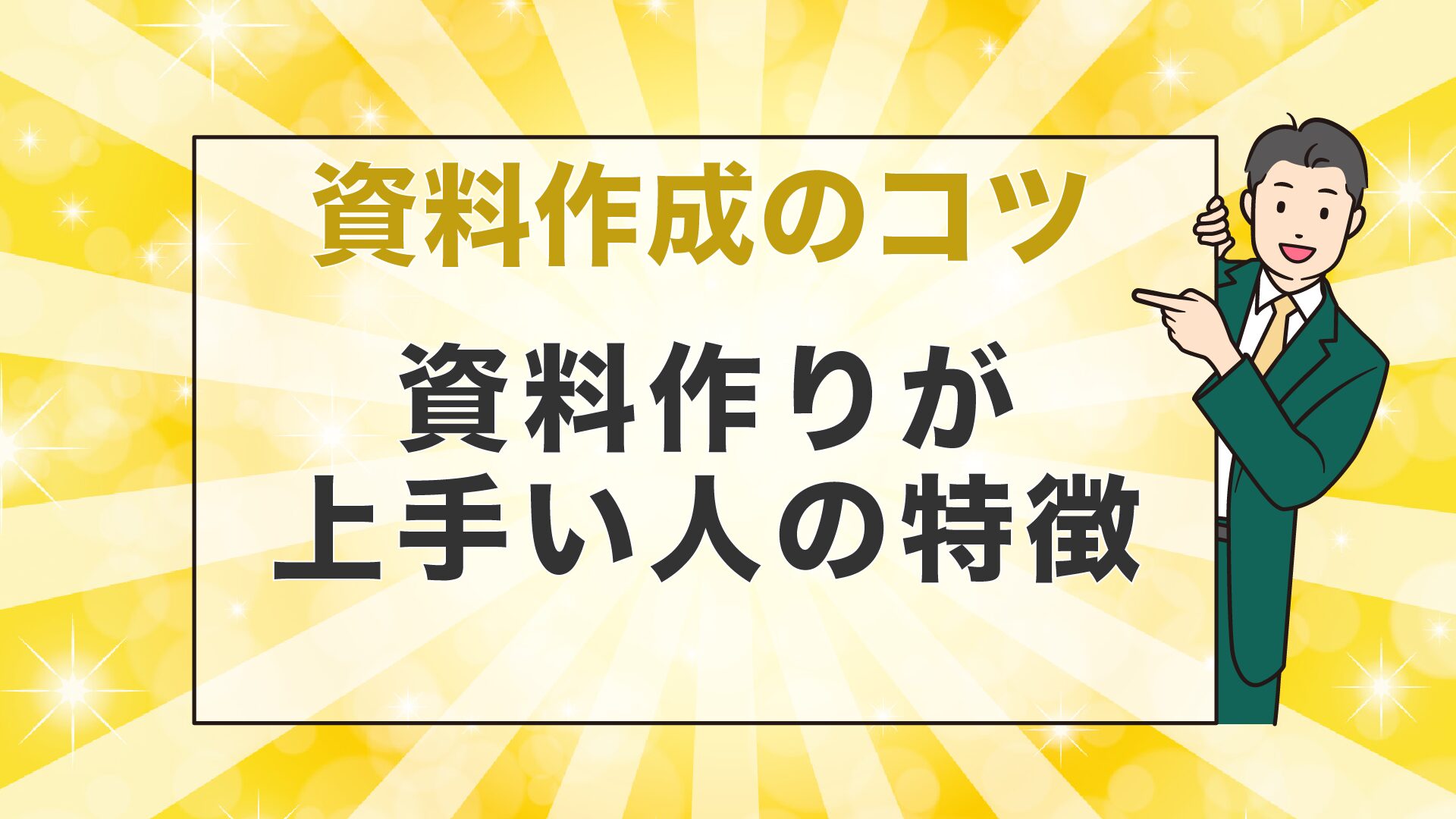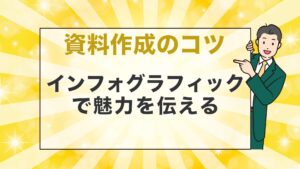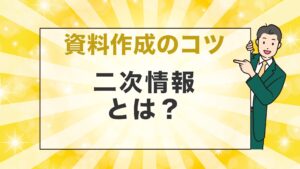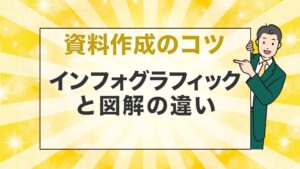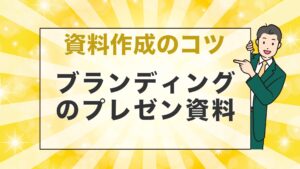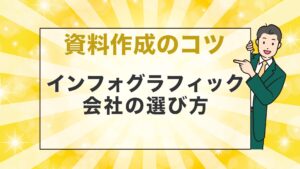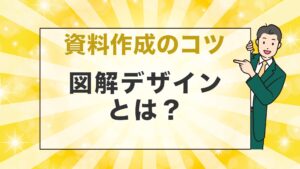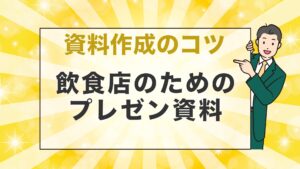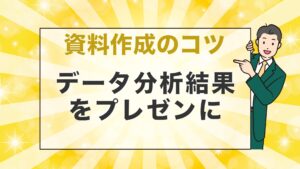資料作りが上手くいかずにいつも時間をかけてしまう?
資料作りができなくても仕事には影響しないと感じている?
資料作りが上手い人にはどんな特徴があるのでしょうか。
この記事では、プレゼン資料を作るのが上手い人の特徴7選と、上手い人が実践しているコツを解説します。さらになぜ上手くなれるのか、コツ自体の習得方法もお伝えします。
実は資料作りの上手い人になるとプレゼンで結果を出しやすく、
自分のビジネスも上手く進みますよ。
資料作りの上手い人はキャリアアップも上手く出世していく

プレゼン資料作りの上手さは、あなたのキャリアアップに直結します。
資料によって、プレゼンのしやすさや結果が左右されるからです。
プレゼンに成功すると、以下のような結果がついてきます。
- 相手に自分の提案が伝わる
- 自分の企画が実現できる
- 自分の実績やポジションアップにつながる
資料作りは誰でもできるタスク。良質な資料をスピーディに作成できれば、プレゼンの先にある責任ある仕事や面白い仕事につながります。
資料作りの上手い人の特徴7選

資料作りの上手い人とは、どんな人なのでしょうか。次の7つの特徴があります。
- 資料の作成目的をつかめている
- プレゼン相手について理解している
- 資料の利用場面をつかめている
- 資料の全体像から構成を作成している
- 簡潔な文章で作成している
- デザインのコツをつかんでいる
- 周囲からフィードバックをもらい修正できている
どれも特別なスキルではなく、基本的なビジネススキルです。詳しく説明します。
資料の作成目的をつかめている
資料作りの上手い人は、作成の目的をおさえています。
プレゼンの目的から逆算すると、資料の構成がはっきりするからです。作成にかける時間や手間も最小限におさえられます。
自分一人だけで目的をつかみきれない場合、上司や関係者とすり合わせておくのもコツです。
プレゼン相手について理解している
資料作りの上手い人は、資料を届けるプレゼン相手のことも理解しています。
こちら側の思いや都合のみを一方通行で表現しては提案が通りません。
以下のポイントは相手によって内容を調整しながら資料を作成しています。
- 特に相手にささるポイントは?
- 提案に対する意思決定者が決済に必要な内容は?
- 相手のニーズや欲しい情報は?
(例:広く情報収集したい、具体的なアイデアを比較検討したい、いますぐ利用できるアイデアに絞って検討したい)

相手の理解できる言葉やイメージは?
プレゼンされる側に立ったつもりでチェックしながら作成を進めています。
資料の利用場面をつかめている
プレゼンには様々な状況があり、資料の利用場面も違います。
資料作りの上手い人は利用場面にあわせて準備し、相手の反応しやすさを引き出しています。
よくある利用場面と資料の工夫は以下のとおりです。
- 対面での営業 → トークを補うデータや図解はもらさず入れておく
- スクリーン投影でのセミナー → 聴き手を引きつける見やすさやわかりやすさに留意
- 見込み客獲得のための資料 → 好印象につながるデザイン性に留意、きっかけにつながる情報を網羅的に掲載
資料の全体像から構成を作成している
プレゼンの目的や相手、利用場面の確認が進むと、資料に入れるべき内容やポイントが洗い出せているはずです。
資料作りの上手い人は全体像から逆算して構成を作成しています。この段階で伝えるべき内容やプレゼンのストーリーも固めています。
プレゼンの構成ポイントは以下も参考になります。
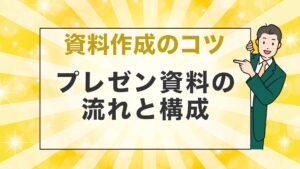
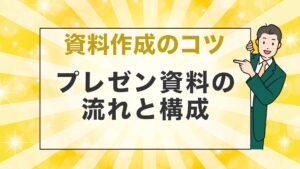
プレゼンの構成に沿って、必要な情報を資料に落とし込んでいくのがコツです。
簡潔な文章で作成している
資料作りの上手い人は、プレゼン資料の文章を簡潔にまとめています。
長い文章や専門用語、あいまいな言葉では相手がプレゼン内容を理解できません。
具体的に、かつ短い文章で、相手がプレゼン内容に疑問を持たないよう伝えるのがポイントです。
相手によりイメージが伝わる言い換え例をご紹介します。
| 言い換えのポイント | 言い換え前の表現 | 言い換え後の表現 |
|---|---|---|
| メリットをより具体的に提示 | 経済的なソリューションを提供します | 低コストを実現します |
| 見通しを数字で具体的に提示 | 中長期的に | 2〜3年後をめどに |
| 誰でも知っている言葉に言い換え | このチームにはマーケティングに強いメンバーをアサインしています | このチームにはマーケティングに強いメンバーに参加してもらいます |
提案をスムーズに通すためにも、相手の理解しやすい文章を心がけましょう。
デザインのコツをつかんでいる
資料のデザインは見やすさに直結します。
資料作りの上手い人にとって、綺麗なスライドを作ることは目的になりません。説明された側が理解しやすいか、説明したいメッセージが伝わるかがポイントです。
資料作りに失敗してしまう人の例を見ると、以下のような資料があげられます。
- 色使いが過剰
- 文字が多い
- 図形や画像が不揃い
相手に「資料が見にくい」印象を持たれないように、デザインのコツをつかんでおきましょう。
周囲からフィードバックをもらい修正できている
資料の完成度を高めるには、周囲からのフィードバックが効果的です。
資料作りの上手い人は、作成者本人では気づけないポイントがあること、自分1人ではチェックに時間がかかることを知っています。
資料の精度を高めるには、周囲の目を借りて以下をチェックすると効果的です。
- 構成に抜け漏れはないか
- 伝わりにくい点がないか
- 誤字脱字など見落としがないか
精度の高い資料はプレゼンで使いやすく、相手からも掲載内容を信頼されます。
資料作りの上手い人に学ぶ!コツをつかんで時間をかけすぎない


資料作りが上手くなるには、どのようにしたら良いのでしょう。上手い人から以下5つのコツを学べます。
- 作成の目的と利用場面を確認する
- 全体の構成から作成する
- PCで作成作業をするのは最後にまわす
- 周囲からフィードバックをもらい手直しする
- デザインの基礎やツールの利用方法をつかんでおく
資料作りのはじめから終わりにかけてコツが存在します。それぞれ詳しく見てみましょう。
作成の目的と利用場面を確認する
まずはプレゼン資料の設定確認です。目的と利用場面をクリアにしましょう。
ビジネス資料の目的は、相手の具体的なアクションにつなげることです。
掲載内容や重点的に伝える点にあいまいな箇所が残らないよう確認してください。
「誰に、何のアクションを取ってもらうのがゴールか」を以下の例で紹介します。
- 部署の上司|社内会議
- 新事業立ち上げの決済をもらいたい
- 課題を伝えて対策案の承認をもらいたい
- 社外のお客様|商談
- 新サービスの魅力を伝えて導入いただきたい
- 既存商品リニューアルの魅力と価格アップの根拠を伝えて値上げ方向での継続購入をいただきたい
資料の目的と利用場面を確認して、方向性や掲載内容を決めてから次に進んでください。
提案資料に必要なポイントやさけたい失敗例は以下の記事も参考になります。
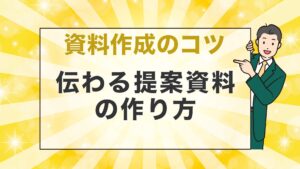
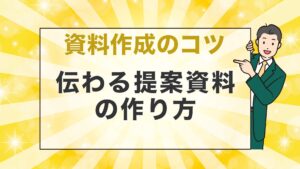
全体の構成から作成する
資料の目的と利用場面が決まると、構成が作成できます。
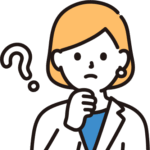
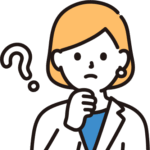
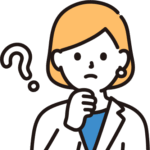
相手が理解しやすく、かつ納得しやすい流れで説明できる構成を目指しましょう。
プレゼンの基本は「導入 → 課題提示 → 解決策 → 結論」の 4ステップです。さらに以下のように、状況に合わせて使いやすい型があります。
- 情報を簡潔にわかりやすく伝える「PREP法」
- 問題解決や交渉、意見を述べたいときに有効な「DESC法」
- 聴き手がポイントを理解しやすい「SDS法」
- マーケティングや営業プレゼンで効果的な「PASONA法」
自分で1から構成を考えるのが苦手な方は、具体的な型にそって組み立てると作業がスムーズです。
PCで作成作業をするのは最後にまわす
構成が決まるとさっそく資料を作りたくなりますが、PCでの作成作業は最後にまわしてください。
「考えながら作る」「材料を集めながら作る」方法は、実は時間の浪費です。
特に文章やデータ類には、他部署からもらう必要がある場合があります。作成前に、使用目的や必要な期限を伝えて協力をあおぎましょう。
また、社外に提示不可の素材があった場合は差し替えが必要になってしまいます。早めに確認して手戻りを防ぎたいですね。
以下の進め方なら、時短につながります。
- 構成にそって必要な要素を手書きで整理する
- スライドの配置を手書きしてスペースに入る文章量や画像の当たりをつける
- 文章のテキストデータを準備する
- 画像やグラフ表などのデータを準備する
全ての素材が揃ってから一気にPCで配置すると、作成作業がスムーズです。
周囲からフィードバックをもらい手直しする
資料がいったん完成したところで、自分での見直しはもちろん、周囲からフィードバックをもらいましょう。
作成している本人は、意外と間違いや伝わりにくいポイントを見落としがちです。
目的を把握している上司からは的確な指摘がもらえます



内容を詳しく知らない同僚にひと目見てもらうだけでケアレスミスや見にくい点が発見できます。
フィードバックを受けたい項目と、チェックをお願いしたい人を以下にまとめました。
| フィードバック項目 | チェックする人 | ||
|---|---|---|---|
| 上司 | 自分 | 同僚や部下 | |
| 目的やターゲット | ●(作成前のすり合わせも有効) | ● | |
| 資料に含める内容や順番(構成) | ● | ● | |
| 掲載内容(特に見積もりなど金額にかかわる点やスケジュール・体制) | ● | ● | |
| 誤字脱字や色使い、フォントのチェック | ● | ● | |
フィードバックを受けた内容を修正すると、より精度の高い資料が完成します。
なお、おひとりあるいは少人数でビジネスを展開している場合には、資料作成をプロに依頼する方法もおすすめです。作成はプロに任せて自分はフィードバックに専念すると、効率的に資料作成が進められます。
デザインの基礎やツールの利用方法をつかんでおく
プレゼン資料のデザインにはコツがあります。
基礎的なルールを心がけるだけでも見やすい資料ができます。また自分で1からデザインする必要はなく、ツールやテンプレートで解決できる部分もあります。
デザインの基本的なスタンスをおさらいしましょう。以下を心がけるだけでも見やすい資料になります。
- 色を使いすぎない
- 要素を詰め込みすぎず余白をとる
- 画像の配置をそろえる
さらにテンプレートを活用するとあらかじめ配置が決まっているため、文章や画像など内容作成に集中できておすすめです。
デザインに頭を悩ませて時間をロスする必要はありません。
デザインのポイントはぜひ以下の記事も参考にしてください。
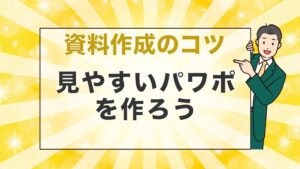
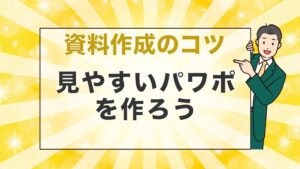
資料作りの上手い人はコツの習得も上手い


資料作りの上手い人は、作成方法のコツを習得するのも上手です。以下2つのコツを紹介します。
- 資料作りが上手い人や好きな人から教えてもらう
- わかりやすい資料の事例にふれておく
2つのコツは、誰でもすぐ試せる方法です。具体的にみていきましょう。
資料作りが上手い人や好きな人から教えてもらう
あなたの周りに、資料作りが上手い人はいませんか。
プレゼンで結果を出している上司や資料作成が早い先輩からテクニックを学ぶのは、もっとも身近な上達方法です。
身近なお手本から、以下の点を吸収しましょう。
- 資料の構成方法
- フォーマットや図表の配置方法
- 関係者へのフィードバック依頼方法
資料作りが上手い人や好きな人は、作成に慣れていて方法を改善しつづけているものです。社内の人なら「コツを教えてほしい」と頼みやすく、コミュニケーションにもつながります。
わかりやすい資料の事例にふれておく
プレゼン資料の作成経験が浅い人なら、事例のストックも役立ちます。
先輩が結果を出した資料や自分が提案を受けてわかりやすかった資料は、どんなところがよかったのでしょうか。
企画書・提案書・スケジュール設定・市場分析・課題分析など、利用したい場面にあわせて整理しておくと役に立ちます。
以下のポイントから事例を見てみてください。
- 構成(論理展開)
- 文章
- 色使い
- デザインの見やすさ
見つかったヒントは自分なりの型に落とし込んでおきましょう。
まとめ:資料作りの上手い人は仕事が速く結果も出せる


今回は、資料作りが上手い人の特徴7選と、上手い人が実践しているコツを解説しました。さらになぜ上手くなれるのか、コツ自体の習得方法もお伝えしました。
資料作りが上達すると時間を効率的に使えて、プレゼンの結果が出しやすくなります。ビジネスの前進や自身のキャリアアップにもつながりますので、この記事を参考にぜひ資料作りのスキルアップにチャレンジしてみてください。
資料作りの苦手な方や多くの資料作りを抱えている場合には、プロへの依頼もおすすめです。
お仕事自動化ラボでは、ビジネスを加速するための自動化サービスを提供しています。お客様の要望にしっかりとお応えするフローを構築しますので、お悩みの方はぜひご相談ください!